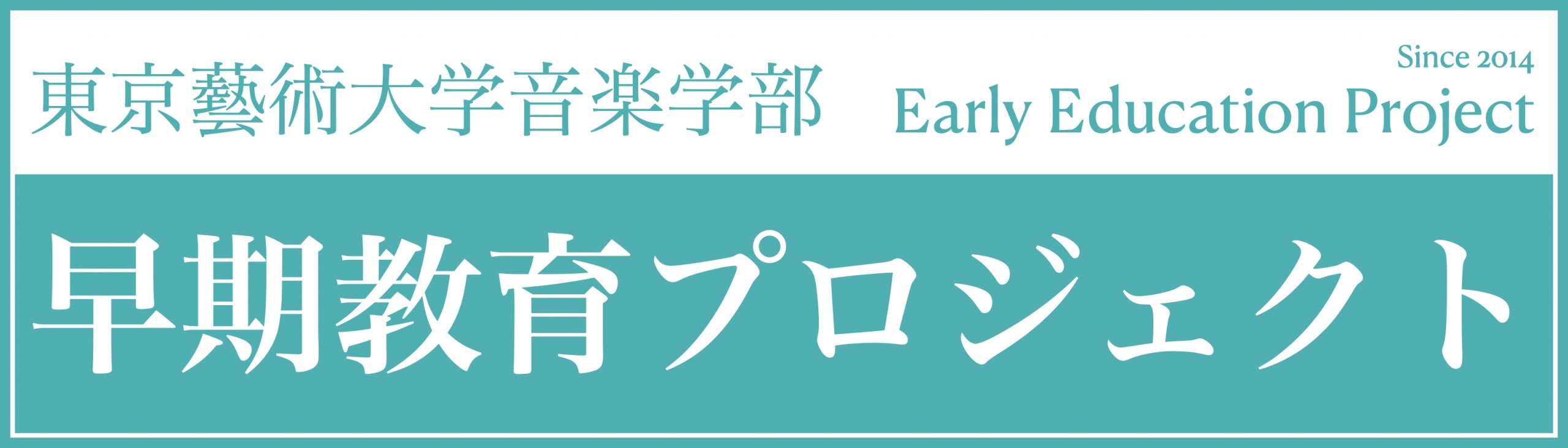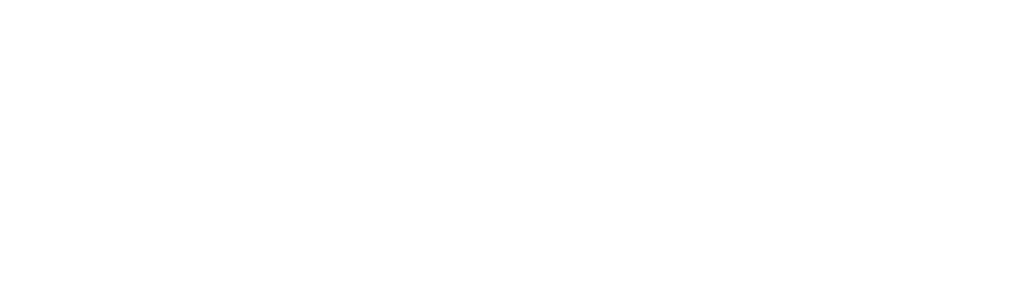- 大学概要
- 学部?研究科?附属機関?センター等
- 展覧会?演奏会情報
- 広報?大学情報
- 学生生活
- 卒業生の方へ
- 一般?企業の方へ
- 教職員の方へ
- 入試情報
- 藝大に寄附をする

第八十一回 西原珉「川の流れのように」
4月に先端芸術表現科に着任してから、気づけば1年が過ぎようとしています。母校である藝大に戻ってきたとはいえ、私が卒業した頃、取手校地は登場の気配もなく。さらに、20年近く日本を離れ、美術とは異なる仕事に没頭していたこともあり、母校の変化にはほとんど気づかずにいました。そうして藝大に戻ったこの1年は、異国に転生した令嬢の心境でした。
藝大には変わらぬ魅力が多くあります。その魅力が、先生方の研究やさまざまな関係者の努力によって継承されていることに敬意を抱く一方で、私はこの1年、新しい価値が生まれる場としての藝大に関心を抱いてきました。現代美術の作品やプロジェクトを通じて、未体験の出来事、未知の感情、思いがけない思考に出会い、それらに心を揺さぶられながら人生の2/3を過ごしてきた私にとって、教育の場としての藝大が何を創り出そうとしているのか——それが大きな関心事だったのです。
先日、藝大の提携校であるスロバキアの国立ブラティスラバ美術デザインアカデミーを訪れ、先端芸術表現科(英語ではInter-Mediaですが強引に和訳)で教授や修士?博士課程の学生たちと話す機会がありました。20年前に設立された向こうの先端の教授が、こんな問いを投げかけました。
「次々と新しい技術とメディアが登場し、トレンドが移ろうアートシーンにおいて、もはや何が先端なのかわからなくなっている」 「私たちが今、学生に伝えるべきものは技術ではなく、世界への態度や価値なのではないか?」
昨年25周年を迎えた藝大の先端(新任ですが)の私と、彼らの抱える課題は驚くほど似通っていたので、夕食どきまで続いた議論の後も、考えることを止められませんでした。表現が自分や他者にもたらすもの——それが物、こと、知覚、何であれ、それが生まれる前にはなかった「何か」を生み出し、人間や人間以外の存在に影響を与える。そこに、私たちは何を見ているのだろうか。変化し続けるアートとともに自らも変わりながら、なお変わらぬ軸としてのアートへの信頼を、どのように伝えていくべきなのか。そんなことを考えながら、気づけばドナウ川の河畔にたどり着いていました。
川は流れ続けることそのものであり、一瞬一瞬の連続です。アートをつくり続ける私たちも運動体として見たらこんな感じなのかもしれません。そして、表現は私たちを取り巻くあらゆるものとつながる手段でもある。
今、取手の研究室の窓から眺める利根川の雄大なうねりは、どこか遠くのポイントでドナウ川につながるのでしょうか。表現されたものが、見えない場所で何かとつながり、新たな価値を生み出していく。そんな信念とともに、川の流れのようにおおらかなアートへの信頼を、これからも伝えていきたいと思っています。

先端芸術表現科1年生の授業 IMA実技 Mindscape

ブラティスラバ美術デザインアカデミーで行った授業風景
写真(上):研究室から利根川を眺める
【プロフィール】
西原珉
東京藝術大学 美術学部先端芸術表現科准教授
東京藝術大学美術学部芸術学科卒業。90年代の現代美術シーンで活動後、渡米。臨床心理学を学び、心理療法士の免許を取得。ロサンゼルスでソーシャルワーカー兼臨床心理療法士として働く。心理療法を行うほか、シニア施設、DVシェルターなどでコミュニティを基盤とするアートプロジェクトを実施した。2018年からは日本を拠点にアーティストや作り手のための相談と心理カウンセリングのほか、アート及びセラピューティックアートを通じたコミュニティのケアに力を注いでいる。2024年4月より秋田市文化創造館館長。