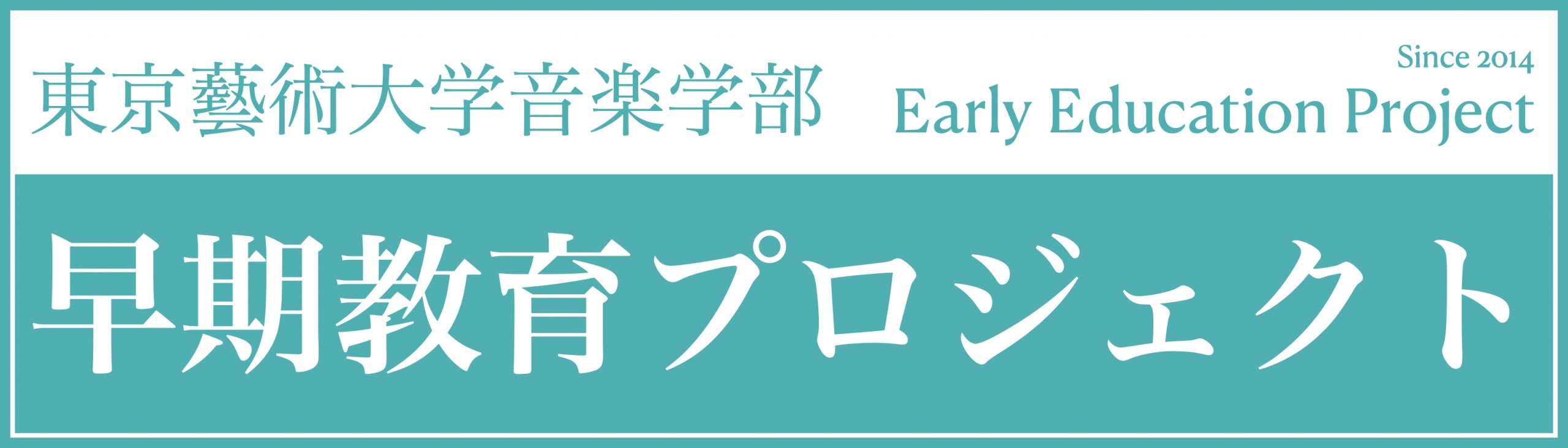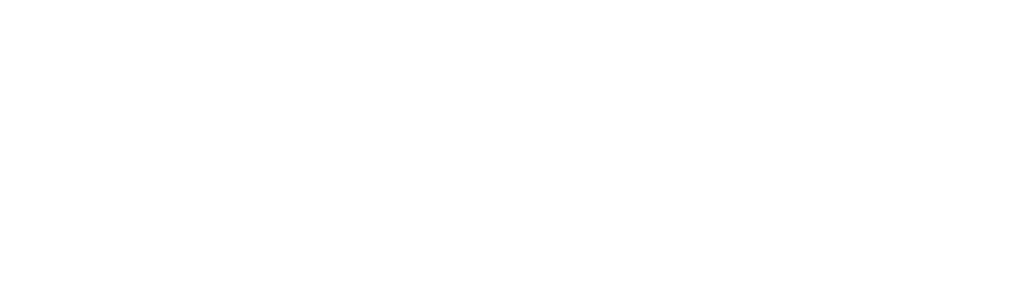- 大学概要
- 学部?研究科?附属機関?センター等
- 展覧会?演奏会情報
- 広報?大学情報
- 学生生活
- 卒業生の方へ
- 一般?企業の方へ
- 教職員の方へ
- 入試情報
- 藝大に寄附をする

第八十五回 齋藤龍一「上野の山の木々の下で」
2024年4月、芸術学科日本?東洋美術史研究室に着任いたしました。上野の山に通うのは、はるか昔、お隣の寛永寺幼稚園に通園した時以来で?大きな木々が自由に枝を伸ばす変わらない光景を日々楽しんでいます。
私の専門分野は、中国美術なかでも仏教?道教美術史で、中国の神さまと仏さまの偶像、すなわち仏像と道教像のすがた?かたちを中心に研究しています。
ご存知の通り、仏教は釈迦を祖としてインドで生まれ日本を含めた東アジアに広く浸透した宗教です。一方の道教は、老子を祖とする中国で生まれた宗教であり、日本で信仰されることはありませんでしたが、その諸要素は仏教?神道?修験道?陰陽道のみならず日々の生活?文化にも影響を与えています。こう説明を進めると、本学と関わりの薄い分野のように感じるかもしれません。
しかながら、そもそも道教美術に関する研究の先鞭をつけたのは岡倉覚三[天心] (1863-1913)でした。岡倉はその著書『茶の本』(Kakuzo Okakura, The Book of Tea,1906)のなかで、?茶道は道教の変装した姿である?とさえ述べ、多くの著作において道教の歴史と老子の思想そしてその美術について紙面を割いています。
また、東京美術学校の教授として日本における東洋美術史研究の礎を築いた大村西崖(1868-1927)は、中国彫刻を美術史研究の立場から取り上げ、その形式?様式について検討し、世界初の中国彫刻研究書である『支那美術史彫塑篇』(仏書刊行会図像部、1915年)を刊行しています。本書は、石造を中心とする中国彫刻を制作年代ごとに分け、さらに仏像と道教像を並立させ論じていることに大きな特徴があります。
つまり、それほど知られてはいませんが、中国仏教?道教美術史は本学にゆかりの深い研究分野でもあるわけです。ちなみに、受け持っている東洋美術史特講?演習は中央棟2階第6講義室で講義をしていますが、窓の外を眺めると斜め下方に大村西崖の胸像が見えます。あまりに近くにいらっしゃる100年前の偉大な先学の存在に、人知れず緊張しています。
何はともあれ、東アジアの真っ只中に暮らし本学で学ぶ皆さんにとって、目指すものは人それぞれでも、仏教?道教美術史のみならずひろく中国美術について知識を得ることは必ずや有益なはずであり、これからも常に最新の研究成果を踏まえつつ、よりわかりやすく紹介していきたいと思っています。

木漏れ日の中の大村西崖像
写真(トップ):3階にもかかわらず、研究室の窓からは木々しか見えません
【プロフィール】
齋藤龍一
東京藝術大学 美術学部芸術学科准教授
中国?北京大学考古学系留学をへて成城大学大学院博士後期課程単位取得退学、筑波大学より博士(学術)学位授与。
1999年から25年間、大阪市立美術館に彫刻担当学芸員として勤務。主な担当展覧会に「大唐王朝女性の美」、「道教の美術」、「岸田劉生」、「山の神仏:吉野?熊野?高野」、「北魏石造仏教彫刻の展開」、「木×仏像」、「仏像 中国?日本」、「聖徳太子日出づる処の天子」など。
著書に『中国道教像研究』法蔵館、共編に『増補改訂版道教美術の可能性』勉誠社、共監訳に『中国道教美術史漢魏晋南北朝篇』勉誠出版など。
論文に「中国南北朝時代の敦煌莫高窟における中心柱窟の展開」、「中国雲岡石窟における中心柱窟の展開とその影響」、「中国南北朝時代後期?隋時代の山西省天龍山石窟における如来像の一考察」、「関野貞による山西?天龍山石窟「発見」をめぐって」など。